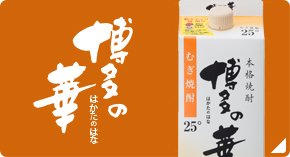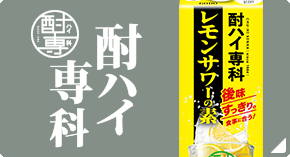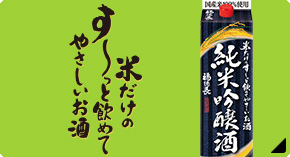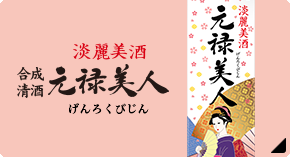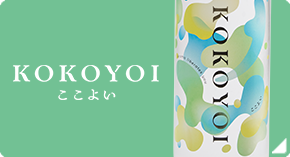日本酒(清酒)についてのよくあるご質問
- 日本酒度・酸度・アミノ酸度とは何ですか?
- 「清酒」はどのように保管すればよいですか?
- 「清酒」の賞味期限はいつですか?
- 「清酒」のカロリーはいくらですか?
- 「清酒」と「合成清酒」の違いは何ですか?
- 「合成清酒」を料理酒として使っても大丈夫ですか?
- 「合成清酒」は「清酒」に比べて、プリン体が少ないと聞きましたが本当ですか?
- 「合成清酒」は「清酒」に比べてどうして安いのですか?
- 「合成清酒」はどのように保管すればよいですか?
- 日本酒(清酒)の原料米とはどのようなものですか?
- 米麹(こめこうじ)とは何ですか?
- 醸造アルコールとは何ですか?
- 「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」の違いは何ですか?
- 「生酒」と「生貯蔵酒」の違いは何ですか?
- 「生(き)もと造り」と「山廃(やまはい)造り(山廃仕込)」とは何ですか?
- 「上撰」「佳撰」とは何ですか?
- 精米歩合とは何ですか?
- お燗の適温は何度でしょうか?
- 「米だけのお酒」を購入、「純米酒ではありません」と記載してあります。
日本酒度・酸度・アミノ酸度とは何ですか?
清酒の味は、「甘・辛・酸・苦・渋」5つあるといわれています。そこで、甘辛の目安として「日本酒度」という基準が設けられました。清酒と水との比重を比較して水より軽ければプラス(辛口)、重ければマイナス(甘口)とし、含まれる糖分が多い場合は比重が重く、甘口のお酒(マイナス)に、逆に糖分が少ないと比重は軽くなり、辛口のお酒(プラス)となります。
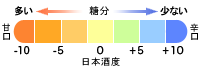
また、「酸度」は清酒に含まれる有機酸(コハク酸、乳酸、リンゴ酸など)の量を示す数値で味の濃淡に影響を及ぼします。一般に酸度が高い(数値が高い)と甘味が打ち消され、辛口で濃醇な味わいになり、酸度が低い(数値が低い)と、甘口で淡麗な味わいに感じられます。 この他、アミノ酸度(清酒に含まれるアミノ酸類の量を示す数値)も味わいに影響を及ぼし、アミノ酸度が高いと濃厚で旨みが多く、低いと淡白に感じられます。しかし、味覚は個人個人で感じ方が異なりますので、これらの値はひとつの目安とお考えください。
「清酒」はどのように保管すればよいですか?
清酒は、特に光と熱に弱く、蛍光灯の光にも敏感に反応しますので、必ず冷暗所に保管してください。臭いの強い場所も避けてください。また、生酒は冷蔵庫に保管の上、お早めにお召し上がりください。
「清酒」の賞味期限はいつですか?
清酒は冷暗所で保管され、未開封の状態では品質変化がゆっくりと進みます。そのため、製造日を表示し、賞味期限は表示しておりませんが一般的には製造日より1年程度で消費されることをお勧めしています。生酒や吟醸酒のように、種類によっては、それより早く(製造日より6か月程度)消費されることをお勧めしている清酒もあります。古くなった“未開栓”の清酒は、料理用などにお使いいただける場合もございます。また、開封された清酒は、お早めにお召し上がりください。
「清酒」のカロリーはいくらですか?
アルコール分が15%の清酒では、100mlあたり平均で約105kcalです。アルコール分が1%低くなると、平均で約5kcal減少します。(当社調べ)
なお、同じ銘柄でも、酒質・仕様などそれぞれの商品設計の違いにより数値は異なります。
「清酒」と「合成清酒」の違いは何ですか?
清酒は日本古来のお酒であり、「日本酒」とも呼ばれます。米と米麹に清酒酵母を加えて発酵させます。発酵終了前に殺菌や酵母の活動を止めるため、醸造アルコール等を添加(純米酒を除く)して、ろ過したものが清酒の原酒になります。
一方、合成清酒は、主食として米の重要性が今よりずっと高かった戦前において、「米をあまり使わなくても清酒の特性を備えたお酒が出来ないか」と研究され、考案されました。清酒と同様な製法で原酒を造り、それに醸造アルコールと糖類、アミノ酸などを加えて製造します。1940年(昭和15年)の酒税法改正で「合成清酒」と命名されました。
「合成清酒」を料理酒として使っても大丈夫ですか?
合成清酒は、清酒の酒質を目指したお酒ですので、料理酒としてお使いいただけます。その調理効果は、清酒と同様に、素材本来の味を引き立てるほか、生臭さをとり、コクを与え、味の浸透を促進させます。そのため、和食、洋食、中華料理などすべての料理にお使いいただけます。アルコールを含む調味料として他に「本みりん」がありますが、こちらは照り、ツヤ、甘さを加える料理に適しています。
「合成清酒」は「清酒」に比べて、プリン体が少ないと聞きましたが本当ですか?
清酒は、米、米麹を原材料に、発酵によってアルコールや旨み成分が造られる醸造酒です。一方、合成清酒は、清酒をベースに、ブレンドして造った混成酒と呼ばれるお酒です。一般的に、合成清酒のプリン体は清酒に比べて低い数値となっています。
「合成清酒」は「清酒」に比べてどうして安いのですか?
合成清酒は、清酒と比べると酒税が安く、また原材料も異なります。また、清酒より製造期間が短く、大量生産による効率的な生産やコスト削減が可能なため、より低価格での供給が可能なのです。
「合成清酒」はどのように保管すればよいですか?
清酒と同じように冷暗所に保管してください。温度変化で風味が劣化する場合がありますので、高温になる場所は避けてください。清酒と比べ、合成清酒はアルコール度数が低い商品もあり、開栓されると空気中の雑菌に影響される場合があります。開封後は、お早めにお召し上がりください。
日本酒(清酒)の原料米とはどのようなものですか?
一般に、日本酒の原料となるお米として「酒造好適米」と「一般米」を使用いたします。「酒造好適米」は、大粒でタンパク質や灰分、脂肪分の含有量が少なく、また、麹がつくりやすく、酒母(しゅぼ)や醪(もろみ)の製造過程で酵素作用を受けやすいお米です。代表的なお米としては、「山田錦」などがあります。
米麹(こめこうじ)とは何ですか?
蒸米に麹菌(こうじきん)を繁殖させたものです。米麹に繁殖した麹菌から色々な酵素が分泌されます。主な役割は蒸米を溶かし、アルコール発酵するために白米のでんぷんをブドウ糖に変えることです(糖化)。また、たんぱく質をアミノ酸などに分解し、旨み成分を付与します。特定名称酒(吟醸酒・純米酒・本醸造酒)は、このこうじ米の使用割合が15%以上と清酒造りの法律で決められています。
醸造アルコールとは何ですか?
日本酒に使われる醸造アルコールは、「米」や「サトウキビ」などのデンプン質や糖質を発酵させ連続蒸留機で蒸留してつくられるエチルアルコールです(一般的に、アルコール度数は約95%)。従って、化学的に合成したアルコールとは異なります。
この醸造アルコールは、清酒醪(もろみ)の発酵末期に添加しますが、その量には制限があり、吟醸酒や本醸造酒では、原料として使う白米重量の10%を超えないこととされています。この技術は江戸時代の「柱焼酎」にまで遡り長年かけて確立した技術で、香りが高く、スッキリとした淡麗で軽快な酒質とするための有効な手段となります。
また、アルコールを添加することで日本酒の香味を悪くさせる火落菌(乳酸菌の一種)に対する耐性や、抵抗力が強くなり、保存性が高まります。
「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」の違いは何ですか?
これらは日本酒の造りの違いを示す名称で、特定名称酒と呼ばれています。これらの表示がない日本酒は一般酒(普通酒)となります。
「吟醸酒」とは、精米歩合60%以下の白米を原料に、低温でゆっくりと発酵させて造られます。そのため、きれいですっきりとした滑らかな味と、吟醸香と呼ばれるリンゴやバナナなどの果実香が特徴となっています。
この吟醸酒には醸造アルコールを使用するタイプ(吟醸酒)と使用しない純米タイプ(純米吟醸酒)があります。さらに、精米歩合が50%以下の白米を使用するとそれぞれ大吟醸と純米大吟醸となります。
「純米酒」とは、米及び米麹と水だけを原料として造った清酒のことです。従来は精米歩合70%以下の要件がありましたが、醸造設備の開発や製造技術の進歩などにより、この精米歩合70%以下の要件を満たさなくても純米酒の品質に匹敵するものができるようになりました。そのため平成15年10月に「清酒の製法品質表示基準」の一部が改正され、精米歩合70%以下の要件が削除されました。
「純米酒」は醸造アルコールを添加しないので一般的には酸度が高く、濃醇なタイプのお酒となります。
なお、「純米酒」と「純米酒ではない米だけの酒」は、いずれも米及び米麹と水だけを原料とします。しかし、純米酒の製法品質表示基準である
・こうじ米使用割合は15%以上
・白米は農産物検査法により、3等以上に格付けされた玄米またはこれに相当する玄米を精米したもの
が満たされない場合は、「純米酒」という表示はできません。
この純米酒基準を満たさない清酒に「米だけの酒」と表示することはできますが、「純米酒ではありません」と明確にわかる説明表示をしなければなりません。
「本醸造酒」は、精米歩合が70%以下で、米、米麹、醸造アルコールと水で造ります。醸造アルコール(アルコール分100%換算)の使用は制限があり、白米重量の10%を超えない範囲での使用となります。一般的には切れが良く、辛口タイプのお酒となります。
特定名称酒の製法品質表示基準:(平成15年10月改正)
| 名称 | 原材料 | 精米歩合 | その他の要件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特定名称酒 | 吟醸酒 | 純米大吟醸酒 | 米・米こうじ | 50%以下 | 吟醸造り 固有の香味と色沢が特に良好 |
| 大吟醸酒 | 米・米こうじ 醸造アルコール |
||||
| 純米吟醸酒 | 米・米こうじ | 60%以下 | 吟醸造り 固有の香味と色沢が良好 |
||
| 吟醸酒 | 米・米こうじ 醸造アルコール |
||||
| 純米酒 | 特別純米酒 | 米・米こうじ | 60%以下又は特別な製造方法 | 香味と色沢が特に良好 | |
| 純米酒 | 米・米こうじ | ― | 香味と色沢が良好 | ||
| 本醸造酒 | 特別本醸造酒 | 米・米こうじ 醸造アルコール |
60%以下又は特別な製造方法 | 香味と色沢が特に良好 | |
| 本醸造酒 | 米・米こうじ 醸造アルコール |
70%以下 | 香味と色沢が良好 |
(注)
※白米は農産物検査法により、3等以上に格付けされた玄米またはこれに相当する玄米を精米したものを使用。
※こうじ米使用割合は15%以上。
※醸造アルコール(アルコール分は100%換算)の量は、白米の重量の10%以下。
「生酒」と「生貯蔵酒」の違いは何ですか?
一般に日本酒は製造後と出荷前の2度熱処理を行います。これを「火入れ」といいます。これは、発酵を止め、雑菌の繁殖を防ぐためと、酒質を保つために行います。
しかし、特殊フィルターによるろ過技術の進歩と冷蔵技術並びに低温輸送の発達により、一度も「火入れ」を行わないでお客様にお届けすることが可能となりました。このように一度も「火入れ」しないお酒を「生酒」といいます。
一方、「火入れ」しないで生酒として低温貯蔵し、出荷前に1度だけ「火入れ」を行ったお酒を「生貯蔵酒」といいます。搾りたてのフレッシュな風味をお楽しみいただくため、当社では「生酒」はできるだけ早くお召し上がりいただくことをお勧めしています。また、「生貯蔵酒」は製造日より、半年から遅くとも1年程度でお召し上がりいただくことをお勧めしています。
「生(き)もと造り」と「山廃(やまはい)造り(山廃仕込)」とは何ですか?
日本酒造りは、水と米こうじと蒸した米を基に乳酸の力を借りて健全な酵母菌を培養させる「酒母(しゅぼ)」(「酛(もと)」ともいいます)造りからスタートします。
この乳酸を酒母にどう取り込むかによって「造り」の呼称がかわります。
「生もと造り」は、空気中の自然の乳酸菌を取り込んで乳酸を生成させ、時間をかけて酒母を造っていきます。この「生もと造り」には半切桶(140L~360L)に入れた米、米こうじ、仕込み水を、櫂をつかってすりつぶす「山卸し」の作業を伴います。この「山卸し」の作業は厳寒期に数時間行われる大変過酷な作業でした。その後、明治末期に麹の酵素が自然に米粒を溶解させることが判明し、「山卸し」の作業を廃止する方法が考案され、「山卸し廃止もと」といわれるようになったことから「山廃造り(山廃仕込)」といわれるようになりました。
一方、「山廃造り」が考案された同時期に、自然の乳酸菌による乳酸の生成を待たずに、はじめから乳酸を添加し、更に純粋培養した酵母を加えた酒母造りが開発されました。これを「速醸もと(速醸仕込)」といいます。
この「速醸仕込」は、雑菌に汚染されずに安全に醸造できることと、手間もかからず仕込み日数も「山廃仕込」に比べ短縮して造れる利点があり、現在では「速醸仕込」が主流となっています。
一般に「山廃造り」のお酒は、濃厚でコクがあり、「速醸仕込」のお酒は淡麗でキレがあるといわれていますが、醸造技術の向上により、それぞれの造りによる味わいの差は無くなっているとも言われています。
「上撰」「佳撰」とは何ですか?
お客様が商品をお選びいただく際のひとつの目安として、当社では自社の日本酒をランク付けし、「上撰」「佳撰」という呼称で独自に選別しています。
1992年4月1日以降、「特級」「1級」「2級」という級別制度が廃止されました。そのため、級別に代わって自社の基準に従って商品をランク付けいたしました。
「上撰」は主に「特級」「1級」の商品群をまた、佳撰は「1級」「2級」の商品群をランク付けしています。
精米歩合とは何ですか?
玄米に対する白米の重量パーセントのことです。お米の表層部には、多くのタンパク質や脂肪、灰分、ビタミンなどが含まれています。これらが多すぎると、できあがった清酒の味や香りが悪くなるため精米によって表層部を削っています。
例えば、精米歩合70%というと、玄米の表層部を30%削ることをいいます。なお、通常家庭で食べているお米は、92%程度といわれています。
お燗の適温は何度でしょうか?
「米だけのお酒」を購入、「純米酒ではありません」と記載してあります。
純米酒と表示するためには、白米は農産物検査法により3等以上に格付けされた玄米またはこれに相当する玄米を精米したものを使用し、更にこうじ米使用割合は15%以上でなければなりません。したがって、規格外のお米を使用しているかこうじ米の比率が低い場合は、純米酒とは表示できません。